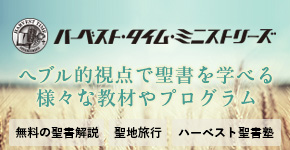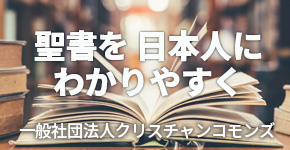旧約聖書におけるメシア預言
レジュメ(4)2025年7/12
代名詞としての「シロ」と地名の「シロ」とはヘブル語ではスペルが異なると聞き一同驚愕
人を表わす「シロ」が出てくる聖句は1か所だけのよう
2007年フルクテンバウム博士セミナー
『旧約聖書におけるメシア預言』
THE MESSIAH OF THE OLD TESTAMENT
By Dr. Arnold Fruchtenbaum
(テキスト)
ご購入はこちらから(CD)(テキスト)
フルクテンバウム博士のメッセージを
中川健一牧師がわかり易く通訳してくださった
セミナーの内容を基に作成しています。
以下
青色の聖句はセミナーでとりあげられた聖句箇所です
(セミナーでは新改訳3を使用しています)
(このHPでの引用聖句は原則 口語訳聖書 旧約聖書1955年改訳 新約聖書1954年改訳 日本聖書協会)
「新改訳3」とは聖書 新改訳 ©1970,1978,2003 新日本聖書刊行会
「新共同訳」とは聖書 新共同訳©共同訳聖書実行委員会j
「新改訳2017」とは聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会 からの引用です
黒色の文章がセミナーの説明文
緑色の文章はHP編者による補足説明
紫色の聖句は引用聖句や参考聖句
(英語訳は基本American Standard Version ASV)
マロン色の文章はアーノルド・フルクテンバウム博士著/佐野剛史訳『メシア的キリスト論
ー旧約聖書のメシア預言で読み解くイエスの生涯ー』からの補足説明です。
興味のある箇所はリンク先もご覧になってみてください。
紙の聖書「新改訳2017」はこちらをどうぞ
旧約聖書におけるメシア預言
イントロダクション
Ⅰ.律法
A.「女の子孫」
B.「アブラハムの子孫」
C.「ユダの子孫」
Ⅰ.律法
セミナーテキスト4ページ(6/15)
C.「ユダの子孫」
創49:10
[初臨の預言]
創世記49:10
創 49:10 つえはユダを離れず、
立法者のつえはその足の間を離れることなく、
シロの来る時までに及ぶであろう。
もろもろの民は彼に従う。
(以下断りがなければ口語訳)
創 49:10 王権はユダを離れず、
統治者の杖はその足の間を離れることはない。
ついにはシロが来て、
国々の民は彼に従う。
(新改訳3)
Gen 49:10 The sceptre shall not depart from Judah,
Nor the ruler’s staff from between his feet,
Until Shiloh come;
And unto him shall the obedience of the peoples be.
(ASVのthyはyour thouはyou saithはsays ほか と以下表記します)
メシアが到来するまでは
ユダ部族が12部族の中で最も優位性(他の部族を治める部族というアイデンティティや統治権)を持った部族であるという預言
またユダ部族が存在するということ
これはそのまま継続されるということ
もう一回言う
メシアが来るまではユダ部族の優位性とアイデンティティーが壊れることはないと預言している
そして「シロ」が来たならば異邦人たちもまたこの方に従うようになる
国々の民:異邦人のこと
(創49章は神さまがヤコブの12人の息子たち全てをとおしてアブラハム契約を継続することを追認したことが書かれている箇所。ヤコブの遺言であり、10節はユダに対する預言です。)
「シロ」という言葉の意味
シロ:時にはメシアを指すメシアの名前であるという説明がなされることがあるがこれは名詞ではない
名詞として固有名詞としてとるべきではなく
権威がその方に所属しているところのお方という
所有代名詞のようにとらなければいけない
もう一回言う
これは名詞ではなくて代名詞
直訳すると
権威がその方に所属しているところのお方というような意味
エゼキエル書21:25~27
[再臨の預言]
このシロの預言 創世記49章の預言と非常によく似た預言が
エゼキエル書21:25~27に出てくる
エゼ 21:25 汚れた悪人であるイスラエルの君よ(反キリスト)、あなたの終りの刑罰の時であるその日が来る。
Eze 21:25 And you, O deadly wounded wicked one, the prince of Israel, whose day is come, in the time of the iniquity of the end,
21:26 主なる神はこう言われる、かぶり物を脱ぎ、冠を取り離せ。
すべてのものは、そのままには残らない。
卑しい者は高くされ、高い者は卑しくされる。
21:26 thus says the Lord Jehovah: Remove the mitre, and take off the crown; this shall be no more the same; exalt that which is low, and abase that which is high.
イスラエルの王が或る時王位から退けられ
かぶり物は脱がされ、冠は取り去られる(新改訳3)という預言
21:27 ああ破滅、破滅、破滅、わたしはこれをこさせる。
わたしが与える権威をもつ者が来る時まで、その跡形さえも残らない。
21:27 I will overturn, overturn, overturn it: this also shall be no more, until he come whose right it is; and I will give it him.
(ネブカデネザルから反キリストまで「異邦人の時」が続くことを繰り返しヤハウェが述べています。ーF博士のエゼキエル書注解より)
「かぶりもの」
かぶり物とは祭司が被るもの
出 28:4 彼らの作るべき衣服は次のとおりである。
すなわち胸当、エポデ、衣、市松模様の服、帽子 a mitre、帯である。
彼らはあなたの兄弟アロンとその子たちとのために聖なる衣服を作り、祭司としてわたしに仕えさせなければならない。
(新改訳3:かぶり物)
出 28:37 これを青ひもで帽子に付け、それが帽子の前の方に来るようにしなければならない。
出 28:39 あなたは亜麻糸で市松模様に下服を織り、亜麻布で、ずきんを作り、また、帯を色とりどりに織って作らなければならない。
出 29:6 そして彼の頭に帽子をかぶらせ、その帽子の上にかの聖なる冠をいただかせ、
出 39:28 亜麻布で帽子を作り、亜麻布で麗しい頭布を作り、亜麻の撚糸の布で、下ばきを作り、
出 39:31 これに青ひもをつけて、それを帽子の上に結びつけた。主がモーセに命じられたとおりである。
レビ 8:9 その頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なる冠をつけさせた。主がモーセに命じられたとおりである。
レビ 16:4 聖なる亜麻布の服を着、亜麻布のももひきをその身にまとい、亜麻布の帯をしめ、亜麻布の帽子をかぶらなければならない。
これらは聖なる衣服である。彼は水に身をすすいで、これを着なければならない。
「冠」
冠とは王がかぶるもの
(テキストに「冠」の聖句箇所として挙げられている下の聖句箇所に冠はでてきません。
でてくるのは「王笏」「つえ」です。)
創 49:10 王笏 The sceptre はユダから離れず
統治の杖 the ruler’s staff は足の間から離れない。
ついにシロが来て、諸国の民は彼に従う。
(新共同訳)
(王笏が王権を象徴しています。
エゼキエル書では王冠がその代わりをしています。
統治の杖とは統治権)
直訳すると
「王笏はユダから離れず、
統治の杖は足の間から離れない。
しかし、それは権威を帯びた者が来るまでのことである。
諸国の民はその方に従う。」
(冒頭の聖句、初臨の預言)
詩 [ 110 ]
ダビデの歌
110:1 主(ヤハウェ)はわが主(ダビデの「主」メシア)に言われる、
「わたしがあなたのもろもろの敵(シオン)を
あなたの足台とするまで、わたしの右に座せよ」(同格の存在)と。
110:2 主はあなたの力あるつえをシオンから出される。
あなたはもろもろの敵のなかで治めよ。
(ダビデの主メシアはダビデの子孫であり、神と同格の存在、神人です。
初臨で民に拒絶されたメシアはしばらく天の神の右の座に着座しているよう招かれました。)
110:3 あなたの民は、あなたがその軍勢を
聖なる山々に導く日に
心から喜んでおのれをささげるであろう。
あなたの若者は朝の胎から出る露のように
あなたに来るであろう。
110:4 主は誓いを立てて、み心を変えられることはない、
「あなたはメルキゼデクの位(創14章)にしたがって
とこしえに祭司である」。
(メシアの敵の心が変えられ、メシアが王として再臨する時、喜んで仕える民となります。
メルキゼデクの位の祭司とは王であり祭司(人間)である存在ですが、モーセの律法では王はユダ族、祭司はレビ族の家系でないとなれないと規定していて、王と祭司は兼任できません。
つまりこの預言の成就の為にはモーセの律法とレビ的祭司制度が取り除かれる必要があります。)
110:5 主はあなたの右におられて、
その怒りの日に王たちを打ち破られる。
110:6 主はもろもろの国のなかでさばきを行い、
しかばねをもって満たし、
広い地を治める首領たちを打ち破られる。
110:7 彼は道のほとりの川からくんで飲み、
それによって、そのこうべをあげるであろう。
(テーマは再臨、メシア的王国ではメシアがイスラエルを統治します。)
祭司職も王の職も取り去られてイスラエルは廃墟になる
それがいつまで続くかというと
わたしが授ける権威を持つ者つまりメシアが来るまでそれが続くということ
イスラエルに王がなくなったのが
バビロン捕囚の時
イスラエルに祭司がいなくなったのは
紀元70年にローマによって滅ぼされた時
その王がない状態(紀元前586年以降)
祭司が取り去られた状態が(紀元70年以降)
メシアが到来する(再臨)まで継続する
創世記49:10にシロという言葉がでた
これは権威がその方に属しているところのお方という意味だと言った
それとエゼキエル21:27の
「わたしが授ける権威を持つ者」という言葉とはイコール
これは同じ人物を指している
もう1回くりかえすと
メシアが登場する(初臨 2千年前のキリスト誕生)まではユダ部族はその優位性を失うことはないという預言の内容になる
三つの教え
ここからメシアに関して三つの教えが語られる
1.人類から、アブラハムから、そしてユダ族から
第一番目がメシアはアブラハムの子孫として出るのだがその中の12部族のユダ部族から出てくることがここで明らかになる
だんだんメシアが出てくる範囲が狭まっていく
全人類 そしてアブラハム 12部族 ユダ部族と範囲が狭まっている
テキストの前のページ3ページ
ダビデ契約
Ⅰ歴代17:10b~14
歴代上 17:10 a わたしはまたあなたのもろもろの敵を征服する。
かつわたしは主があなたのために家 a house を建てられることを告げる。
17:11 あなたの日が満ち、あなたの先祖たちの所へ行かねばならぬとき、わたしはあなたの子、すなわちあなたの子らのひとりを、あなたのあとに立てて、その王国を堅くする。
~ that I will set up your seed after you, who shall be of your sons; and I will establish his kingdom.
17:12 彼はわたしのために家 a house を建てるであろう。
わたしは長く彼の位 his throne を堅くする。
17:13 わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となる。
わたしは、わたしのいつくしみを、あなたのさきにあった者から取り去ったように、彼からは取り去らない。
17:14 かえって、わたしは彼を長くわたしの家に、わたしの王国に in my house and in my kingdom すえおく。
彼の位 his throne はとこしえに堅く立つであろう』」。
この箇所でダビデ契約というのが結ばれるが
ここでメシアはユダ部族の中のダビデの家系から出てくると範囲がさらに狭まる
(神はダビデに3つのことを約束しています。
1.とこしえの家(王朝)
2.とこしえの王国
3.とこしえの王座)
2.メシアは王である。
2つ目に注目すべきはここで杖という言葉が出てくるが
これは王さまが持つ杖のこと(王笏)
だからメシアは王であるということがわかる
3.ユダ族の存在が明白なうちにメシアは登場する。
紀元70年の前に登場する。
3つ目に言えることは
メシアの登場(初臨)は紀元70年になる前に登場していなければこの預言にあわないということがわかる
皆さんイスラエル12部族の系図はどこで保管されていたかご存知か?
神殿の中
神殿が滅びたのが紀元何年か?
70年
ということは神殿が滅びて以降は系図がなくなってしまった
だから各々の部族は自分が何部族に属しているかをもはや証明できなくなった
これが紀元70年
それ以降自分がダビデの系図に属しているということがわからなくなるわけだからメシアはそうなる前に登場していないとおかしい
紀元70年以降数百年の間にダビデの家系が誰かわからない
また自分が何部族か分からないという状態が普通になる
一つの例外はレビ族
レビ族だけは自分の部族がなんであるかがわかった
さっき言ったようにメシアは紀元70年に神殿が滅びる前に登場しなければ理屈に合わないということがここで分かる
・・・・・・・
今確認のための質問をした
創世記49章はメシアの初臨に関する預言
エゼキエル21章はメシアの再臨に関する預言
ここでこの二つを並べた理由は何かというと
シロという言葉と同じ言葉がエゼキエルで使われているということを
その言葉の意味を証明するためにこの箇所を引用している
ただ内容は初臨と再臨と方向性が違う
そのことを今確認しておいてほしい
・・・・・・・
結論
(1)「女の子孫」と「アブラハムの子孫」は、ユダ部族から出る。
(2)メシアは、王である。
(3)メシアは、紀元70年の前に登場する。
ここまでで結論は
メシアは紀元70年の前に登場しなければならない
ユダヤ部族から出てくる王としてのメシアであるということ
ここまでがはっきりした
メシア預言(5)2025年8/30へ
Ⅰ.律法 D.「バラムの預言」民数記22章と24章
アーノルド・フルクテンバウム博士著/佐野剛史訳
『メシア的キリスト論
ー旧約聖書のメシア預言で読み解くイエスの生涯ー』
ハーベスト・タイム・ミニストリーズ出版部
今回のセミナーの内容はこの本の12頁~に、
詩篇110:1~7については127頁~
1歴17:10b~14ダビデ契約については110頁~に書かれています。