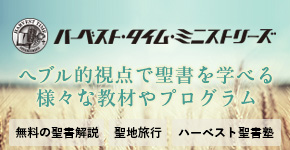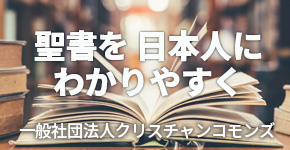旧約聖書におけるメシア預言
レジュメ(9)2025年10/25
イザ7:14のアルマーは創3:15の女を指す
無信仰なアハズ王であってもダビデ契約の故に神さまは励ましと約束を与える
2007年フルクテンバウム博士セミナー
『旧約聖書におけるメシア預言』
THE MESSIAH OF THE OLD TESTAMENT
By Dr. Arnold Fruchtenbaum
(テキスト)
ご購入はこちらから(CD)(テキスト)
フルクテンバウム博士のメッセージを
中川健一牧師がわかり易く通訳してくださった
セミナーの内容を基に作成しています。
以下
青色の聖句はセミナーでとりあげられた聖句箇所です
(セミナーでは新改訳3を使用しています)
(このHPでの引用聖句は原則 口語訳聖書 旧約聖書1955年改訳 新約聖書1954年改訳 日本聖書協会)
「新改訳3」とは聖書 新改訳 ©1970,1978,2003 新日本聖書刊行会
「新共同訳」とは聖書 新共同訳©共同訳聖書実行委員会j
「新改訳2017」とは聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会 からの引用です
黒色の文章がセミナーの説明文
緑色の文章はHP編者による補足説明
紫色の聖句は引用聖句や参考聖句
(英語訳は基本American Standard Version ASV)
マロン色の文章はアーノルド・フルクテンバウム博士著/佐野剛史訳『メシア的キリスト論
ー旧約聖書のメシア預言で読み解くイエスの生涯ー』p.39~41の抜粋補足説明です。
マゼンタ色の文章はDr. Arnold G. Fruchtenbaum ARIEL聖書注解シリーズ イザヤ書 The Book of Isaiah
私家訳版 イザヤ書第6章からの補足説明です
興味のある箇所はリンク先もご覧になってみてください。
紙の聖書「新改訳2017」はこちらをどうぞ
旧約聖書におけるメシア預言
イントロダクション
Ⅰ.律法
A.「女の子孫」
B.「アブラハムの子孫」
C.「ユダの子孫」
D.「バラムの預言」
E.「モーセのような預言者」
F.律法のまとめ
Ⅱ.預言書
A.イザヤ書7:1~21 処女から生まれる
1.ダビデの家に対する脅威 イザヤ7:1~2
2.アハズ王へのメッセージ イザヤ7:3~9
3.解放のしるし イザヤ7:10~17
a.しるしの提供 7:10~11
b.しるしの拒否 7:12
c.ダビデの家に対するしるし 7:13~14
ヘブル語の「アルマー(乙女)」
d.アハズに対するしるし 7:15~17
4.アッシリヤの侵攻 イザヤ7:18~21
結論
セミナーテキスト9(11/15)ページ
Ⅱ.預言書
A.イザヤ書
7:1~21
処女から生まれる
セミナーテキスト9ページ
3.解放のしるし
イザヤ7:10~17
c.ダビデの家に対するしるし 7:13~14
前回のつづき
13~14節
イザ 7:13 そこでイザヤは言った、
「ダビデの家よ、聞け。
あなたがたは人を煩わすことを小さい事とし、またわが神をも煩わそうとするのか。
7:14 それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。
見よ、おとめ a virgin ハ・アルマー がみごもって男の子を産む。
その名はインマヌエルととなえられる。
おとめ 処女(新改訳3):ヘブル語で(3)アルマーということば
ここで使われている「処女」という言葉の前にはヘブル語の定冠詞ハがつく
ザ・バージンという言い方になる
セミナーテキスト8ページ
ヘブル語の
「アルマー(乙女)」
ヘブル語で3種類のお互いに言い換えあうことができる言葉がある
(1)ナアラー
ヘブル語のナアラー:若い女の子 少女
を指す言葉
この言葉は処女に使ってもいいし
そうでない人に使ってもいい
Ⅰ列王記1:2
列王上 1:2 その家来たちは彼に言った、
「王わが主のために、ひとりの若いおとめ a young virgin (1)ナアラー を捜し求めて王にはべらせ、王の付添いとし、あなたのふところに寝て、王わが主を暖めさせましょう」。
おとめ(口語訳) 処女(新改訳3):ナアラー
ところがルツ記2:6
ルツ 2:6 刈る人たちを監督しているしもべは答えた、
「あれはモアブの女 the Moabitish damsel (1)ナアラー で、モアブの地からナオミと一緒に帰ってきたのですが、
ナアラーという言葉が処女でない若い女性に使われている
(2)べツラー
ベツラーは「処女」を表わす現代ヘブル語である。
しかし古典へブル語では、一般的に
ベツラー:年齢に関係なしに独身でいる女性のことを指す言葉
特に処女を指す場合にこの言葉が使われることがあるが 例外もある
ラビたちはこう言う
もしイザヤがメシアの処女降誕を預言したかったら(3)アルマー(乙女)という言葉ではなくて
(2)べツラーという言葉を使っていたはずだ
しかし(2)ベツラーという言葉が100%処女を指すかというとそうとも言えない
処女以外の女性を指す場合にこの言葉が使われることがあるから
だから聖書でベツラーという言葉が使われるとその意味が何であるかを詳しく説明しないと処女か処女でないかの区別ができないというタイプの言葉
例えば創世記24:16
リベカに関して
創 24:16a その娘 the damsel (1)ナアラー は非常に美しく、男を知らぬ処女 a virgin (2)べツラー であった。
娘:(1)ナアラー
処女:(2)ベツラー
もしこのベツラーという言葉が100%処女を指すなら
その娘は非常に美しく、処女で、(新改訳3)でいいわけだが意味を解説している
男が触れたことがなかった。(新改訳3) neither had any man known her という解説が出ている
日本語聖書では処女と訳しているが
ベツラーという言葉は処女でない場合にも使われるので
わざわざ男が触れたことがなかった。という補足説明をしている
もしここでベツラーということばではなくて
(3)アルマーという言葉が使われていたならこういう説明を付け加える必要がなくなる
士師記21:12
士 21:12 こうして彼らはヤベシ・ギレアデの住民のうちで四百人の若い処女 four hundred young virgins (2)べツラー を獲た。
これはまだ男と寝たことがなく、男を知らない者である。
彼らはこれをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきた。
処女:ベツラー
もしベツラーが100%処女を意味しているのであればそれだけでいいわけだが
ここでは男と寝たことがなく、男を知らないという修飾節をつけている
ベツラーという言葉が処女である場合とない場合があるのでそれを明確にするためにそういう説明を頭に付けている
これらからわかるのはベツラーという言葉は
処女を指す場合もあるし
或いは処女でない女性を指す場合もある
ヨエル書1:8が非常に興味深い例
ヨエ 1:8 あなたがたは若い時の夫のために
荒布を腰にまとったおとめ a virgin (2)べツラー のように泣き悲しめ。
おとめ:ベツラー
ここでこのおとめは未亡人になっている
これは若い時に夫を亡くして荒布をまとって嘆いている若い未亡人
これはつまり処女ではない
つい最近夫を亡くした若い女性
イザヤ7:14では(1)ナアラーということばも(2)ベツラーという言葉も使っていない
その理由はこの二つの言葉は処女を指すこともあれば処女でない女性を指すこともあるという二つの意味を持ったことばだから
(3)アルマー almah
イザヤ書7章にもう1回かえる
アルマーという言葉がどういう言葉かを確認する
アルマーの頭には定冠詞ハがついている
つまりthe virginという言い方になる
・・・
あえて訳せば「その処女」
「その」という言葉が出てきたらすぐ直前の文脈で「その」に該当するもの人物がないかを探す
キングジェイムズヴァージョンKJV ニューアメリカンスタンダードヴァージョンNASV アメリカンスタンダートヴァージョンASVでは a virginとなっている。
イザヤ書7章で言及されている女性はいないのでハが a と訳されている理由かもしれない。
すぐ直前にそういう女性が登場していないならもっと広い文脈でこの言葉の意味を探さなければならない
創世記3:15の「女の子孫」と約束されていたあの「女」がザ・バージンになる
創 3:15 わたしは恨みをおく、
おまえと女とのあいだに、
おまえのすえと女のすえとの間に。
彼はおまえのかしらを砕き、
おまえは彼のかかとを砕くであろう」。
・・・(割愛)
知識のあるカトリック教徒であれば聖母マリアこそマドンナであると誰でも知っている
それと同じでイザヤの時代に聖書に精通しているユダヤ人にザ・バージン ヘブル語でハ(ヘブル語のザ)・アルマー
と言ったらそれが創世記3:15の「女の子孫」のあの「女」を指していると常識としてわかった
ここでイザヤはメシアは処女から生まれると初めて預言した
もう一つ別な意味からこれが処女懐胎であると説明したい
皆さんはヘブル語で書かれた旧約聖書がギリシャ語訳に訳されたことはご存じか
この旧約聖書のヘブル語のギリシャ語訳というのはイエスさまが生まれる250年ほど前におよそ70人の学者によって完成したのでこのギリシャ語訳のことを70人訳と言う
このギリシャ語訳を実は新約聖書が旧約聖書を引用する時によく用いている
新約聖書はギリシャ語で書かれている
ヘブル語の聖書から自分が訳して引用するのではなく既にあった70人訳のギリシャ語を引用して新約聖書に書いてあるという関係にある
ここの(3)アルマー 処女という言葉:
ギリシャ語訳70人訳ではパーセノス
ギリシャ語でパーセノス:
適齢期を迎えた若い女性のことを指す
結婚した女性或いは歳をとった女性に使うことは一回もない
若い未婚の女性を指す
もし未婚の若い女性が子どもを産むとしたら
二つの可能性しかない
①処女懐胎か
②姦淫のゆえに子供を産むか
②若い年齢の女性が不義を働いて子供を産むとしたらしるしにはなり得ない
この時代そんなに頻繁にはないが 今だったら婚外子はいくらでもある
これは自然現象だからしるしにはならない
ここでイザヤが言っている神からの超自然的しるしとはかけ離れている
ここでは神さまがこのしるしをつくりだしているわけなのでこれは超自然的なものでなければおかしい
①処女が身ごもって子供を産むとしたらまさにそれは超自然的なしるしとなり得るもの
イザヤ書以外の書を見るとこのパーセノス処女という言葉は6回使われていて
すべて処女の女性をさしている
その女性が処女であることを明らかに語っている箇所がでてくる
このパーセノスということばは
6回の例を見ると
明らかに処女であると書いてある場所と
処女であるとは明らかには書いていないが
処女でないとは書いてない
つまり処女である可能性が非常に高いという言葉
決して結婚した女性にパーセノスという言葉が使われることはない
創世記24:43
この箇所はリベカに関する言及で
創 24:43 わたしはこの泉のそばに立っていますが、水をくみに出てくる娘 the maiden (3)ハ・アルマー に向かって、
「お願いです。
あなたの水がめの水を少し飲ませてください」
と言い、
既にリベカは男と寝たことがないということばが出てきた
創 24:16a その娘 the damsel (1)ナアラー は非常に美しく、男を知らぬ処女 a virgin (2)べツラーであった。
先ほど(2)で見たようにリベカについてはベツラーということばが16節では使われてその意味を説明していた
しかし43節にいくとアルマーということばになっていてもはや処女であることは確実なのでそれ以上説明する必要がない
セミナーテキスト9ページ
出エジプト記2:8
出 2:8 パロの娘が
「行ってきてください」
と言うと、少女は行ってその子の母を呼んでき た。
2:8 パロの娘が
「そうしておくれ」
と言ったので、おとめ the maiden (3)ハ・アルマー は行って、その子の母を呼んで来た。
モーセのお姉さんミリアムに関する言及
ミリアムは不道徳な女性であると聖書のどこにも書かれていないので独身であるとは彼女が処女であることを暗示している
(ミリアムは独身?この聖句の時のミリアムは幼いのでは?という疑問がだされました。)
詩篇68:25
詩 68:25 歌う者は前に行き、琴をひく者はあとになり、
おとめら the damsels (3)アラモテ(アルマーの複数形)はその間にあって手鼓を打って言う、
評判の良い女性が神さまをたたえる行列に参加している
雅歌1:3
雅 1:3 あなたのにおい油はかんばしく、あなたの名は注がれたにおい油のようです。
それゆえ、おとめたち the virgins (3)アラモテ はあなたを愛するのです。
人々の賞賛を得るにふさわしい女性が登場する
雅歌6:8
雅 6:8 王妃 queens は六十人、そばめ concubines は八十人、また数しれぬおとめ virgins (3)アラモテ がいる。
アルマーという女性が王の妻或いはそばめとは区別された若い女性として描かれている
王妃:王の子供を産んで王位を継承する子供たちがそこから生まれてくる立場の女性
そばめ:王の慰めのために置かれる女性でその彼女たちが子供を産んでも王位を継承することはない
王妃とかそばめは既に処女ではない
おとめたち(新改訳3):やがてそばめになる為に準備をしている人たちでこの段階では処女
箴言30:18~19
箴 30:18 わたしにとって不思議にたえないことが三つある、
いや、四つあって、わたしには悟ることができない。
30:19 すなわち空を飛ぶはげたかの道、
岩の上を這うへびの道、
海をはしる舟の道、
男の女 a maiden (3)アルマーにあう道がそれである。
おとめ(新改訳3)
非常に真面目な不道徳ではない女性のことが描かれている
20節に出てくる姦通する女(新改訳3)との対比の中で出てくる
箴 30:20 遊女 an adulterous woman の道もまたそうだ、
彼女は食べて、その口をぬぐって、
「わたしは何もわるいことはしない」
と言う。
19節
私は4つ不思議だ 知らないと
つまり処女ならば男性とともにいる時に或いは男性からの誘惑にあった時にどういう風に反応するかわからない 予測できないんだと
ところが20節にいくと姦通する女の場合は予測できると
彼女は食べて口をぬぐい、(新改訳3)とある
だから姦通する女(新改訳3) 遊女(口語訳)という言葉と
おとめ(新改訳3) 女(口語訳)アルマーという言葉とが対比されているとわかる
ここでわかることはこのアルマーということばは結婚している女性には使わない
また処女でない女性にも明らかに使っているケースはない
(そうとは断言できないという意見も参加者からだされました。)
イザヤ書7:14の文脈は超自然的な神のしるしが起こることを要求している文脈
イザ7:14 それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。
見よ、おとめ a virgin ハ・アルマー がみごもって男の子を産む。
その名はインマヌエルととなえられる。
それは創世記3:15のメシア預言をより解説するための預言になっている
この処女アルマーということばが結婚をしていない女性を指すわけなので
そこから子供が生まれるとしたら二つの可能性しかない
①結婚していないが姦淫によって子どもをみごもりそして生んでいるという場合
②神が処女を用いてしるしとして子供を誕生させるという可能性
①結婚していない女性が姦淫でみごもったとなるとこれはしるしと呼べるものではなくなる(超自然ではない)
②結婚していない処女がみごもって男の子を生むならばこれはまさに神ご自身がなさるしるしであると言える(超自然的)
ここでのポイント
*ダビデの家は処女から生まれるメシアが登場するまではそのアイデンティティその形を失うことはないという預言になる
*7:14の最後は「その名を『インマヌエル』と名づける。」ということばで終わっている
聖書では親が子供に名前をつける時にその子供の性質
未来を表すような名前をつけるがそのとおりになる場合とそうでない場合とがある
しかし神さまが名前を付ける場合は文字通りその子の性質を言い表した名前になる
インマヌエル:神は我らと共におられるという意味
神は我らと共におられるつまりここでも神人という概念 神であり人であるという概念が出ている
この処女から男の子が生まれるというのは
イザヤが語ってから700年も経ってようやく成就する預言
そこでさっき言った質問
700年後に起こることがアハズ王にとって何の意味があるか
ある意味これは非常に意味のある反論
例えば今皆さんが人生の中の重大な危機に直面していて私のところにアドバイスを求めてきたとする
私がこう言う
心配しないで 神さまから語りかけがあったよ
あなたのこの問題は必ず祝福のうちに終わるから
私が言ったことが正確にそうだということを示すためにあなたにしるしを与えよう
今日から700年後にこうこうこういったことが起こるからねとあなたに言ったとする
700年後と聞いてもそれでホッとする人あんまりいないのではないかなと思う
ここにいる人はみんな700年後にはいなくなるから
私の言ったことが成就したかどうかというのは問う人もいなくなる
だからある意味と言ったのはそういうこと
アハズ王にとっては慰めにならないのではないかというのは確かに正しいポイント
そこで大事なのは二重言及の原則というのが効いてくる
10~12節まで
「あなた」という単数形の代名詞を使い
アハズに語りかけているので
アハズに対する預言だとわかる
ところが13~14節までは
「あなたがた」という複数形の代名詞になっていて
ダビデの家全体に対する預言であると分かる
d.アハズに対するしるし
7:15~17
15~17節
イザ 7:15 その子が悪を捨て、善を選ぶことを知るころになって、凝乳と、蜂蜜とを食べる。
7:16 それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりの王の地は捨てられるからである。
7:17 主はエフライム(北王国イスラエル)がユダから分れた時からこのかた、臨んだことのないような日をあなたと、あなたの民と、あなたの父の家とに臨ませられる。
それはアッスリヤの王である」。
Isa 7:15 Butter and honey shall he eat, when he knoweth to refuse the evil, and choose the good. 7:16 For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land whose two kings thou abhorrest shall be forsaken. 7:17 Jehovah will bring upon thee and upon thy people, and upon thy father’s house, days that have not come, from the day that Ephraim departed from Judah–even the king of Assyria
15~17節に入ると再び「あなた」という言葉が単数形の「あなた」になる
ダビデの家でなくアハズ個人に語りかけ
アハズ王にとって意味のある預言が語られている
16節
イザ 7:16 それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりの王の地は捨てられるからである。
「それは、まだその子が、」(新改訳3)
その子: ザという冠詞がついているので「その子」あるいは「この子」
その子が誰かというのは直前の文脈を見る
直前を見ると確かにひとりの子が出てくる
14節の男の子ではなく、3節にさかのぼってイザヤの息子を指している。
そう考える以外、息子を連れて行くようにイザヤが命じられた理由が見当たらないではないか。
3節で
イザ 7:3 その時、主はイザヤに言われた、
「今、あなたとあなたの子シャル・ヤシュブと共に出て行って、布さらしの野へ行く大路に沿う上の池の水道の端でアハズに会い、
イザヤは「シェアル・ヤシュブ(新改訳3)」という自分の子どもを連れて行っている
ここ7:1~17ではしるしが2つある#
ダビデの家に対するしるし:
処女から生まれる男の子
700年後に生まれるメシア
アハズに対するしるし:
シェアル・ヤシュブ
イザヤが連れてきた自分の息子
「その子(新改訳3)」或いは「この子」イザヤの子が「悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、(新改訳3)」
つまりまだ善悪を選びとれるほどの年齢にならないうちに「あなたが恐れているふたりの王」は征服される。
このことは歴史上翌年に起こっている
「土地は、捨てられ(新改訳3)」とある
ふたりの王とは次の二人
北王国イスラエルの王ペカと
スリヤ(口語訳) アラム(新改訳3) Suriaシリアの王レチン(口語訳) レツィン(新改訳3)Rezin
北王国イスラエルの王
(名前はぺカ Pekah the son of Remaliah)に関しては
セミナーテキストには載っていない聖書箇所
Ⅱ列王記15:29~30
列王下 15:29 イスラエルの王ペカ(レマルヤの子 紀元前737?~732年在位)の世に、アッスリヤの王テグラテピレセルが来て、イヨン、アベル・ベテマアカ、ヤノア、ケデシ、ハゾル、ギレアデ、ガリラヤ、ナフタリの全地を取り、人々をアッスリヤへ捕え移した。
15:30 時にエラの子ホセア(北王国イスラエルの最後の王となる 紀元前732~722年在位)は徒党を結んで、レマリヤの子ペカに敵し、彼を撃ち殺し、彼に代って王となった。
これはウジヤの子ヨタム(南王国ユダのアハズ王の前の王)の第二十年であった。
セミナーテキストには載っていない聖書箇所
アラムの王(名前はレチンRezin)に関しては
Ⅱ列王記16:9にこれが起こっている
列王下 16:9 アッスリヤの王は彼の願いを聞きいれた。
すなわちアッスリヤの王はダマスコ(アラムSyria)に攻め上って、これを取り、その民をキルに捕え移し、またレヂンを殺した。
神を信じなければアハズは長くたつことはできない
# イザヤ7章は、ユダの王アハズが敵国の侵略という脅威にさらされている場面である。
また、その侵略は、アハズ個人だけでなく、ダビデ家全体を脅かすものであった。
そこで神は預言者イザヤを通して、平安を保ち、恐れないようにとアハズに語りかける。
そして、そうできる理由として、神の守りがあることを保証する2つのしるしが与えられる。
1.ダビデ家を滅ぼそうとする試みは処女から男の子が生まれるまでは成就しない
2.アハズ個人に与えられた神の約束は、イスラエルとシリアによる攻撃は成功しないこと
イザヤの息子が善悪の区別がつく年齢になるまでに二人の王は地上から消し去られる
というものであった。
セミナーテキスト9ページ
4.アッシリヤの侵攻
イザヤ7:18~21
そしてアッシリアの攻撃がありアハズ(南王国ユダの王)がアッシリアに滅ぼされてしまう
イザヤ36章を開いてほしい(聖句はこの最後にのせました。)
さきほどのアッシリアの侵攻
イザヤ7:18~21
イザ 7:18 その日、主はエジプトの川々の源にいる、はえを招き、アッスリヤの地にいる蜂を呼ばれる。
7:19 彼らはみな来て、険しい谷、岩の裂け目、すべてのいばら、すべての牧場の上にとどまる。
(・・・あらゆる水飲み場に巣くう。(新改訳2017 ))
7:20 その日、主は大川の向こうから雇ったかみそり、すなわちアッスリヤの王をもって、頭と足の毛とをそり、また、ひげをも除き去られる。
7:21 その日、人は若い雌牛一頭と羊二頭を飼い、
アハズ(南王国ユダの王 紀元前735~715年在位)がアッシリアに囲まれる
アハズの次がヒゼキヤ(紀元前715または716~687年 在位)という王さま
ヒゼキヤはほとんどの場合イザヤの預言に従ったいわゆる善王
良い王さま
しかし一度ヒゼキヤ王がイザヤの指示に反抗して従わなかったことがあった
その結果アッシリアの王がエルサレムに攻めて来て危機に陥った時があった
そこでアッシリアの王はヒゼキヤに使者を送って警告のことばを届ける
イザヤ書36:2でそのアッシリアの王が送った特使(ラブシャケ)がどこに立っているかを見てみよう
セミナーテキストにこの聖書箇所は載っていません
イザヤ書36:2
イザ 36:2 アッスリヤの王はラキシからラブシャケをエルサレムにつかわし、大軍を率いてヒゼキヤ王のもとへ行かせた。
ラブシャケは布さらしの野へ行く大路に沿う、上の池の水道のかたわらに立った。
覚えてる?(前回の冒頭)
イザ 7:3 その時、主はイザヤに言われた、
「今、あなたとあなたの子シャル・ヤシュブと共に出て行って、布さらしの野へ行く大路に沿う上の池の水道の端でアハズに会い、
この「布さらしの野への大路にある上の池の水道のそば」というのはイザヤがアハズ王に会いに行って警告のことば しるしを求めよと語ったのと全く同じ場所
アハズが神のイザヤから伝えられた言葉を受け取らずアッシリアに信頼した為に
アッシリアがアハズを退けて征服するようになった
(南王国ユダはアッシリアへの朝貢を強いられ事実上属国になった)
アハズが不信仰に陥った結果アッシリアが今南王国ユダを支配するようになっている
この使者が立っている場所がこの場所であるということがそれをしめしている
セミナーテキストには載っていない聖書箇所
イザヤ書36章
イザ 36:1 ヒゼキヤ王(南王国ユダのアハズ王の次の王さま)の第十四年に、アッスリヤの王セナケリブが上ってきて、ユダのすべての堅固な町々を攻め取った。
36:2 アッスリヤの王はラキシからラブシャケをエルサレムにつかわし、大軍を率いてヒゼキヤ王のもとへ行かせた。
ラブシャケは布さらしの野へ行く大路に沿う、上の池の水道のかたわらに立った。
36:3 この時ヒルキヤの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である史官ヨアが彼の所に出てきた。
36:4 ラブシャケは彼らに言った、
「ヒゼキヤに言いなさい、
『大王アッスリヤの王はこう仰せられる、あなたが頼みとする者は何か。
36:5 口先だけの言葉が戦争をする計略と力だと考えるのか。
あなたは今だれを頼んで、わたしにそむいたのか。
36:6 見よ、あなたはかの折れかけている葦のつえエジプトを頼みとしているが、それは人が寄りかかるとき、その人の手を刺し通す。
エジプトの王パロはすべて寄り頼む者にそのようにするのだ。
36:7 しかし、あなたがもし「われわれはわれわれの神、主を頼む」とわたしに言うならば、ヒゼキヤがユダとエルサレムに告げて、「あなたがたはこの祭壇の前で礼拝しなければならない」と言って除いたのは、その神の高き所と祭壇ではなかったのか。
36:8 さあ、今わたしの主君アッスリヤの王とかけをせよ。
もしあなたの方に乗る人があるならば、わたしは馬二千頭を与えよう。
36:9 あなたはエジプトを頼み、戦車と騎兵を請い求めているが、わたしの主君の家来のうちの最も小さい一隊長でさえ、どうして撃退することができようか。
36:10 わたしがこの国を滅ぼすために上ってきたのは、主の許しなしでしたことであろうか。
主はわたしに、この国へ攻め上って、これを滅ぼせと言われたのだ』」。
36:11 その時、エリアキム、セブナおよびヨアはラブシャケに言った、
「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。
わたしたちはそれがわかるからです。
城壁の上にいる民の聞いているところで、わたしたちにユダヤの言葉で話さないでください」。
36:12 しかしラブシャケは言った、
「わたしの主君は、あなたの主君とあなたにだけでなく、城壁の上に座している人々にも、この言葉を告げるために、わたしをつかわされたのではないか。
彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするに至らせるためではないか」。
36:13 そしてラブシャケは立ちあがり、ユダヤの言葉で大声に呼ばわって言った、
「大王、アッスリヤの王の言葉を聞け。
36:14 王はこう仰せられる、
『あなたがたはヒゼキヤに欺かれてはならない。
彼はあなたがたを救い出すことはできない。
36:15 ヒゼキヤが、主は必ずわれわれを救い出される。
この町はアッスリヤの王の手に陥ることはない、と言っても、あなたがたは主を頼みとしてはならない』。
36:16 あなたがたはヒゼキヤの言葉を聞いてはならない。
アッスリヤの王はこう仰せられる、
『あなたがたは、わたしと和ぼくして、わたしに降服せよ。
そうすれば、あなたがたはめいめい自分のぶどうの実を食べ、めいめい自分のいちじくの実を食べ、めいめい自分の井戸の水を飲むことができる。
36:17 やがて、わたしが来て、あなたがたを一つの国へ連れて行く。
それは、あなたがたの国のように穀物とぶどう酒の多い地、パンとぶどう畑の多い地だ。
36:18 ヒゼキヤが、主はわれわれを救われる、と言って、あなたがたを惑わすことのないように気をつけよ。
もろもろの国の神々のうち、どの神がその国をアッスリヤの王の手から救ったか。
36:19 ハマテやアルパデの神々はどこにいるか。
セパルワイムの神々はどこにいるか。
彼らはサマリヤをわたしの手から救い出したか。
36:20 これらの国々のすべての神々のうちに、だれかその国をわたしの手から救い出した者があるか。
主がどうしてエルサレムをわたしの手から救い出すことができよう』」。
36:21 しかし民は黙ってひと言も答えなかった。
王が命じて、「彼に答えてはならない」と言っておいたからである。
36:22 その時ヒルキヤの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である史官ヨアは衣を裂き、ヒゼキヤのもとに来て、ラブシャケの言葉を彼に告げた。
結論
4つの結論
ここまでにカバーした内容は何であったかを確認しよう
(1)メシアは処女から生まれる。
創世記3:15の説明。
創世記3:15にある女の子孫(新改訳3)というのが実は処女から誕生するメシアであることをイザヤ7章は明確にした
創 3:15 わたしは恨みをおく、
おまえと女とのあいだに、
おまえのすえと女のすえとの間に。
彼はおまえのかしらを砕き、
おまえは彼のかかとを砕くであろう」。
(2)メシアは、神人である。
「インマヌエル」 「神が私たちとともにおられる」という言葉から
メシアは神であり人であるということがわかった
マタ 1:23 「見よ、おとめがみごもって男の子を産むであろう。
その名はインマヌエルと呼ばれるであろう」。
これは、「神われらと共にいます」という意味である。
(3)メシアは、王である。
メシアは王として来られる
特にダビデの家から出て来られる王であるということが分かった
(4)メシアは、紀元70年の神殿の崩壊以前に生まれる。
メシアは紀元70年の神殿の崩壊の前にうまれなければいけない
なぜかというと神殿が崩壊して以降はダビデの家に属するという系図が全部なくなってしまうので
メシアがダビデの家から生まれることを確認したり証明したりすることができなくなるから
メシア預言(10)2025年11/15へ
Ⅱ.預言書 B.イザヤ書52:13~53:12 受難の僕
アーノルド・フルクテンバウム博士著/佐野剛史訳
『メシア的キリスト論
ー旧約聖書のメシア預言で読み解くイエスの生涯ー』
ハーベスト・タイム・lミニストリーズ出版部
今回のセミナーの内容はこの本のp.39~41と
重なります。
そちらもゼヒお読みください。
イザヤ7:1~12
イザ 7:1 ユダの王、ウジヤの子ヨタム、その子アハズの時、スリヤの王レヂンとレマリヤの子であるイスラエルの王ペカとが上ってきて、エルサレムを攻めたが勝つことができなかった。
7:2 時に「スリヤがエフライムと同盟している」とダビデの家に告げる者があったので、王の心と民の心とは風に動かされる林の木のように動揺した。
7:3 その時、主はイザヤに言われた、
「今、あなたとあなたの子シャル・ヤシュブと共に出て行って、布さらしの野へ行く大路に沿う上の池の水道の端でアハズに会い、7:4 彼に言いなさい、
『気をつけて、静かにし、恐れてはならない。
レヂンとスリヤおよびレマリヤの子が激しく怒っても、これら二つの燃え残りのくすぶっている切り株のゆえに心を弱くしてはならない。
7:5 スリヤはエフライムおよびレマリヤの子と共にあなたにむかって悪い事を企てて言う、
7:6 「われわれはユダに攻め上って、これを脅かし、われわれのためにこれを破り取り、タビエルの子をそこの王にしよう」と。
7:7 主なる神はこう言われる、この事は決して行われない、また起ることはない。
7:8 スリヤのかしらはダマスコ、ダマスコのかしらはレヂンである。
(六十五年のうちにエフライムは敗れて、国をなさないようになる。)
7:9 エフライムのかしらはサマリヤ、サマリヤのかしらはレマリヤの子である。
もしあなたがたが信じないならば、立つことはできない』」。
7:10 主は再びアハズに告げて言われた、
7:11 「あなたの神、主に一つのしるしを求めよ、陰府のように深い所に、あるいは天のように高い所に求めよ」。
7:12 しかしアハズは言った、
「わたしはそれを求めて、主を試みることをいたしません」。
7:13 そこでイザヤは言った、
「ダビデの家よ、聞け。
あなたがたは人を煩わすことを小さい事とし、またわが神をも煩わそうとするのか。
7:14 それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。
見よ、おとめがみごもって男の子を産む。
その名はインマヌエルととなえられる。
7:15 その子が悪を捨て、善を選ぶことを知るころになって、凝乳と、蜂蜜とを食べる。
7:16 それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりの王の地は捨てられるからである。
7:17 主はエフライムがユダから分れた時からこのかた、臨んだことのないような日をあなたと、あなたの民と、あなたの父の家とに臨ませられる。
それはアッスリヤの王である」。
7:18 その日、主はエジプトの川々の源にいる、はえを招き、アッスリヤの地にいる蜂を呼ばれる。
7:19 彼らはみな来て、険しい谷、岩の裂け目、すべてのいばら、すべての牧場の上にとどまる。
7:20 その日、主は大川の向こうから雇ったかみそり、すなわちアッスリヤの王をもって、頭と足の毛とをそり、また、ひげをも除き去られる。
7:21 その日、人は若い雌牛一頭と羊二頭を飼い、